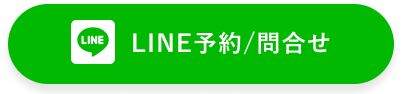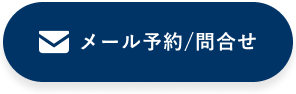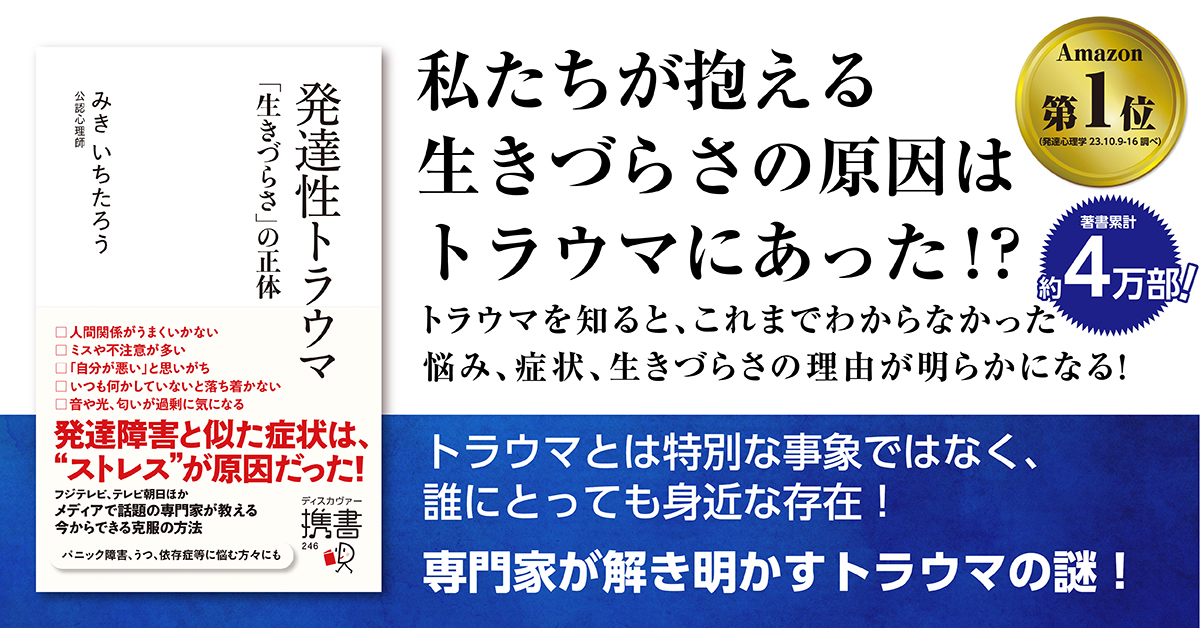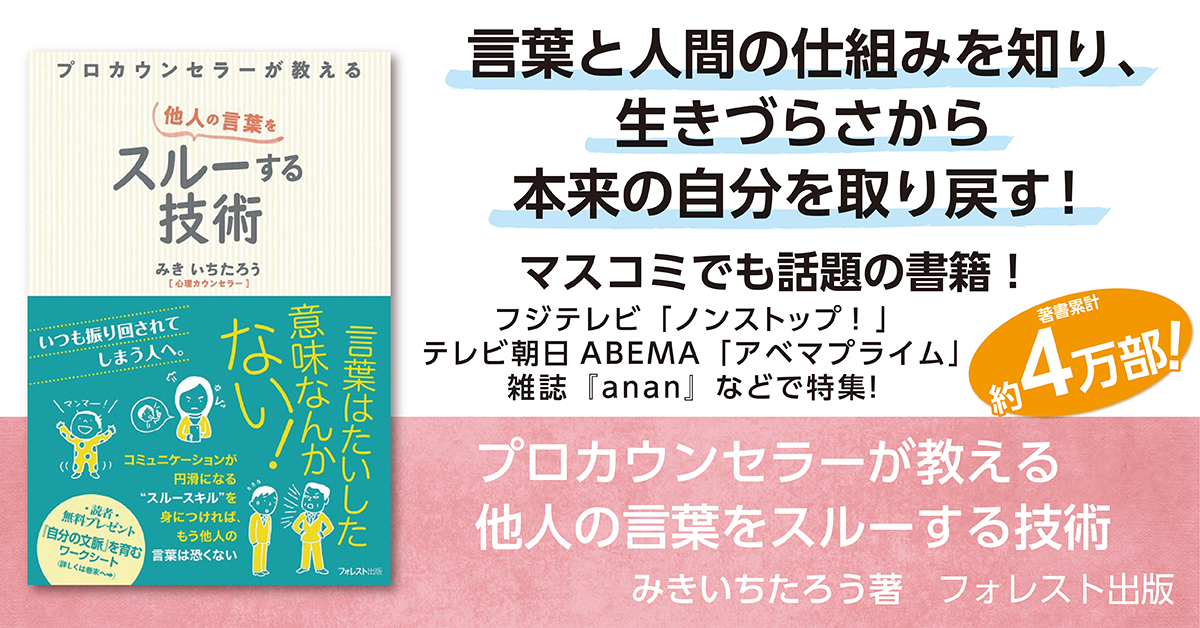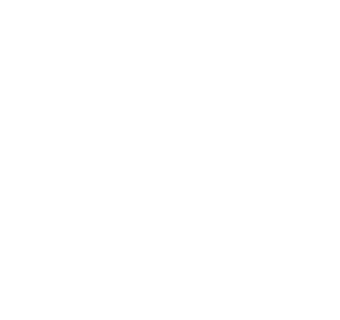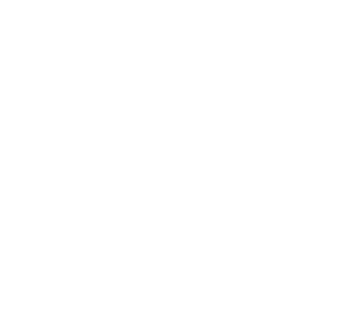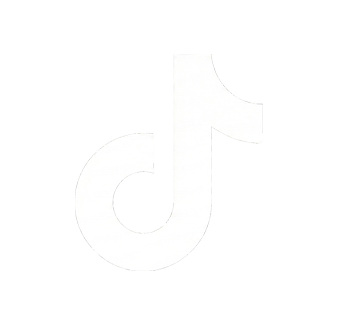悩みの解決に取り組んでいるのに悩みがなかなか良くならない、ということはあります。カウンセリングが行き詰まることもしばしばあります。その原因を検討するのは、決して医師やカウンセラーだけの仕事ではなく、悩みを抱える当事者や家族も主体的に関わる必要のある問題です。無用に自分を責めたり、治療者に対して不信や攻撃を向けたりということは全く建設的なことではありません。なぜなら、あくまで主敵は「悩み」「病気」にこそあるからです。
今回は、医師の監修のもと公認心理師が、悩みがなかなか良くならないときの要因と対応の助けとなるポイント(視点)についてまとめてみました。よろしければご覧ください。
<作成日2016.11.27/最終更新日2025.8.18>
※サイト内のコンテンツを転載などでご利用の際はお手数ですが出典元として当サイト名の記載、あるいはリンクをお願い致します。
 |
この記事の執筆者三木 一太朗(みきいちたろう) 公認心理師 大阪大学卒 大阪大学大学院修士課程修了 20年以上にわたり心理臨床に携わる。様々な悩み、生きづらさの原因となるトラウマ、愛着障害が専門。『発達性トラウマ 「生きづらさ」の正体』など書籍(累計約4万部)、テレビ番組への出演、ドラマの制作協力・監修、ウェブメディア、雑誌への掲載、多数。 |
|---|
この記事の医療監修飯島 慶郎 医師(心療内科、など) 心療内科のみならず、臨床心理士、漢方医、総合診療医でもあり、各分野に精通。特に不定愁訴、自律神経失調症治療を専門としています。プロフィールの詳細はこちら |
<記事執筆ポリシー>
・公認心理師が長年の臨床経験やクライアントの体験を元に(特に愛着やトラウマ臨床の視点から)記述、解説、ポイント提示を行っています。
・管見の限り専門の書籍や客観的なデータを参考にしています。
・可能な限り最新の知見の更新に努めています。
もくじ
・治りにくい、治らない悩みというものはあるのか?
・悩みが治りにくい要因
→なかなか治らない(難治性、遷延性)長引く悩みの治し方については、下記をご覧ください。
治りにくい、治らない悩みというものはあるのか?
まず、精神医学や臨床心理学において、心の悩みのすべてが解明されているわけではありません。そのため、実際に取り組んでいて、「治りにくい」症状があることは事実です。これまではそうしたケースについて「難治性」や「治療抵抗性」といった言葉がつけられてきました。
精神医学自体もまだまだ途上です。それは、心や精神というものが目に見えないことも大きな要因の一つと考えられます。意識が脳や体のどこにあるかさえも現在の科学ではよくわからない状態ですから、“心の果て”を知るまではまだまだ時間がかかりそうです。
精神医学、臨床心理学がこれまで命名してきた病名や症状は、とても粗い網の目のようなものです。実際に悩んでいる当事者からすると、粗すぎてしっくりこないケースも多いでしょう。診断名が付きそこから必勝パターンとされる治療でよくなる良くなる場合もありますが、それからこぼれるものもたくさんあります。明確な診断がつけられないケースもあります。
心というのは、「宇宙」にもたとえられますが、ある意味、医師やカウンセラーも1ケース、1ケースを丹念に探索しながら日々取り組んでいます。
クライアント側もそのことを知ることは大切です。そうすれば、治療者とクライアントが、“病気”“悩み”に対してともに向き合うことが可能になります。最近は、心理教育を徹底したり、行き詰まりを感じたら治療者も正直にそのことを伝えて共に検討するようなスタイルが取られることも多くなりました。そうした姿勢のほうが、打開策が見つかったり、あきらめからくる自殺を防いだりする実際的な効果があるようです。
(参考)治療抵抗性、難治性とは何か?
治療抵抗性、難治性とは、「標準的な治療に十分反応しないこと」と定義されます。ただ、標準的な治療といってもその時に暫定的なものであり、また精神疾患や精神障害はまだまだ明らかになっていないものも多い現状では「治療抵抗性」の中身も便宜的なものであることは否めません。実際、治療者の多くも、治療抵抗性や難治性という言葉に違和感を感じていて、単なる治療者側の力量不足ではないか、といった疑問が示されています。
悩みが治りにくい要因
治りにくい原因がはっきりとわかればその時点で半分解決しているとも言えますから、何が原因かは完全にはわかりません。ただ、これまでの経験の蓄積から、いくつかの要因が指摘されています。まとめてみました。
・見立ての違い~仮説の検証に時間が必要なケース
まず、一番に考えられるのは見立ての違いです。良く知られる例としては、うつ病だと思っていたら双極性障害だったといったことです。家族が怒りっぽいと思っていたら実は痴呆が原因だった、ということもあります。見立てというのはなかなか容易ではありません。
精神障害の症状はスペクトラム状(要素が重なり合っている)をなしているととらえられてきています。そのため、見立ては科学的に単一の原因に帰属されて確定されるというよりも、解決するための手段として最適なものがつけられます。そのため、極端に言えば、Aという診断がつくであろう症状にも、あえてBと判断して進めたほうがしっくりくる、ということはあり得ます。
例えば、最近では、これまでは境界例やパーソナリティ障害などと診断していたものを広義の発達障害傾向と見立てるケースは増えているようです。発達の遅れだとすれば、環境を整えることで成熟を支援して症状を緩和させる、というストーリーが立てられるからです。“解決に向けた診断”が有効なのは、原因が一つではなく無数にあるものだからです。そのため要素に分解して原因を突き詰めて解決に導くということには実は無理があります。それよりも日常生活での問題の緩和や解決を優先するような取り組みが実際的です。
このように見立てはとても大切ですが、見立ては症状だけをチェックリストでチェックすればわかるものではありません。生まれてからどのように過ごしたのか?現在の状況はどうか?性格の傾向。家族との関係。家系での病歴などを聞いて仮説を立てていきます。臨床心理学では通常、心理、社会、生物の3つの観点から見立てていきます。うまくいかない場合は、そのうちの何かの情報が欠けていたり、見立てがあるものだけに偏っていることも多いようです。
科学では仮説をいくつも立てて試行錯誤を繰り返すように、カウンセリングでもいくつもの見立て(仮説)が立てられ検証していきます。そのため、単純に「成功か、失敗か」ということではなく、見立てが外れて、ある可能性が除外されることで解決に近づいていきます。
(参考)発達障害という見立ては解決の役に立つ!?
近年、“発達(障害)”という視点を導入することで、これまでは対応が難しいケース、非定型的なケース、境界例、パーソナリティ障害、例えば統合失調症と診断していたものの多くが「実は“発達障害”なのでは」と言われるようになってきました。これまでは定型発達の人を基準に考えていたために、それにあてはまらないものは「境界例」「非定型」、理解できない人たちは「パーソナリティ障害」とされ、発達(障害)による特徴を見逃してきたのではないか、という提起がなされるようになりました。 実際に、発達という視点を持って取り組むと、それまで動かなかったケースが大きく改善することも珍しくありません。
誰しもが何らかの発達の凸凹を抱えています。負けず嫌いな人、頑固な人、ちょっと独特な雰囲気のある人、全ての人は凸凹しています。治らない“障害”というよりは、気質や環境による“成熟の遅れ”という観点でとらえられています。そのため、成熟を妨げる要因を取り除き、環境を整えることで特徴が目立たなくなり、その人なりに発達をはたすことができるようになると考えられています。
▶「大人の発達障害、アスペルガー症候群とは何か?公認心理師が本質を解説」
・生育歴の問題にアプローチできておらず、対症療法となっている
近年は、愛着障害やトラウマがその後の人生において心身にさまざまな問題を生じさせることが明らかになっています。そうした場合は当然、愛着やトラウマの問題にアプローチする必要があります。しかし、表面的な症状への手当になっており、根本的な要素にアプローチできていないケースがあります。特に病院などでは生育歴を丁寧に聴取する時間が十分に取れないことから対症療法的な手当となっている場合があります。カウンセリングにおいても、愛着やトラウマという視点がなく、「認知」や「行動」レベルの問題になってしまっている場合もあります。このように対症療法的なアプローチになっているために行き詰まってしまう。薬を投与したけど、なぜか良くならないというケースは珍しくありません。
▶「「愛着障害(アタッチメント障害)」とは何か?その特徴と症状」
▶「トラウマ(発達性トラウマ)、PTSD/複雑性PTSDとは何か?原因と症状」
・「躁うつ体質」を見逃しているケース
医師の神田橋條治氏が臨床の中で見出した知見に「躁うつ体質」という問題があります。躁うつ体質というのは文字通りある種の人たちが持つ気質、体質のことです。のびのびした、バラエティに富む人生を欲し、調子に波があり、窮屈な環境では調子を崩しやすく、人との関係の中で生きる、という特徴があります。さらに、内省が不得手で、カウンセリングなどを受けると反対に調子を崩すという傾向があります。躁うつ体質の方が調子を崩した状態を「双極性障害(躁鬱病)」と呼びます。薬などで波を調整しながら、環境も自身に合ったのびのびとしたものへと調整していく必要があります。
躁うつ体質はその事自体を知っている治療者が少なく、また診断も難しいことから、うつ病や他の病気と勘違いされて薬を投与され更に悪化したり。カウンセリングを受けて調子を崩したりということが起きがちです。
▶「双極性障害(躁鬱病)とは何か?実は”体質の問題”という正しい診断と理解」
・「自己の喪失」という視点の欠如
長引く心の悩みで顕著な特徴は何か?というと、「自己の喪失」という問題です。
自分が失われる原因はいくつかあります。愛着不安やトラウマによって自我の形成がうまくいかなくなる。機能不全家族の影響で自分がよくわからなくなる。また、脳や自律神経の失調、社会の中での位置と役割、人間関係がうまくいかないことなどから自分がわからなくなっていってしまうのです(近年問題のヤングケアラーの当事者もしばしば口にする表現は「自分がなくなる」ということは印象的です)。
例えば、心療内科やカウンセリングでは訴えの症状をターゲットにケアが行われます。しかし、ある程度までで限界が来ます。治療者はさらに一生懸命に取り組みますが、手応えとしてもまさに“収穫逓減”という感じでブレークスルーする兆しがなくなります。なぜ変化の兆しがなくなるかというと、様々な症状とは自己を喪失した結果、内的、外的な秩序を回復できないために生じているといっても過言ではありません。そのため症状の改善は自己(セルフ)の再建へのアプローチがなければ進まないのです。改善が行き詰まるケースの多くで、「自己の喪失」という視点が欠如したまま取り組まれていることがあります。
実際に、私のクライアントで最初は症状のケアを行っていて、それからしばらくセッションをお休みされていた方がいました。当時は、私も自己を再建するということは中心に置いていなかったのです。そのクライアントが数年ぶりにケアの依頼をしてこられた際に、自己の再建を踏まえた形でのトラウマケアを行うと、ケアの効き方が全く異なり驚いたことがあります。人間はやはり自己が土台に来なければならないのだ、自己が主体として再建(有力化)されなければならないのだ、と実感したことを覚えています。もし、すでに自分の悩みに取り組まれていて改善が頭打ちになっているとしたら、「自己(セルフ)の喪失、そしてその再建」という視点が念頭にあるか、を点検してみる必要があります。
・必要な時間についての認識の違い
当事者や治療者が当初考えていたよりも、症状が重くてより時間がかかるという場合もあります。ある病が平均で何カ月で良くなるという情報を知っていた場合に、その時期になっても良くならないと「解決していない」と考えてしまうことがあります。しかし、平均というのは簡単言えば半数以上は平均よりも時間がかかることを意味しています。平均とはあくまで参考値であり、各ケースごとにさまざまな偏りがあることは当然です。
実際に、平均よりも時間がかかっていても粘り強く取り組むことで解決できるケースは多いです。例えば、難治性うつで5年たっても良くならないケースでも、その後の5年間で粘り強い取り組みで約4割が回復していることがわかっています。統合失調症でさえ、晩年軽快といい、時間とともに良くなることが知られています。
必要な時間についての認識のズレというのは結構大きいです。多くのクライアントは見切りが早すぎる、というふうに感じます。自分の悩みは重いと感じているにも関わらず、数回のセッションで治るもの、と考えているようなケースがあったり、時間がかかるなら良くならないのだろうと捉えてしまったり。先に予算ありきでまだよくなるにも関わらず早々に打ち切ってしまったりするなどで、自ら機会を失っているようなケースはよくあります。
・解決方法の理解のズレ
魔法の杖を求めて、次々と治療者や方法を変えるドクターショッピングのような状態になっている状態です。上の項目でも書きましたが、一つの方法でも改善までには時間が必要です。また、個別の治療法の選択も大切ですが治療者との信頼関係や自然治癒力への期待も同じくらい大切です。ドクターショッピングになってしまうのはこだわりの強い方、広義の発達障害傾向のある方に多いようです。
(参考)心理療法の技法の違いが及ぼす解決への影響
ラムバートという研究者によると、治療の効果は全体を100とすると、治療外変化(自然治癒力)は40% 共通要因(治療者との信頼)が30% 個別の技法が15% 期待が15% としています。この調査結果については根拠に疑問も示されていますが、うつ病のメタ分析でも、心理療法の共通要因は4割強、個別の治療法は6割弱となっており、うつ病においては個別の治療法の選択が6割近くと上回りますが、共通要因も見逃せない影響があることがわかります。
参考・出典)→丹野義彦など「臨床心理学」(有斐閣)
・症状への認識の違い
人間によって病とは本来の姿にバランスを回復しようとする取り組みであり、症状は実は治療のプロセスという側面があります。例えば、発熱という症状は、それ自体も症状として解熱剤でおさえることもできますが、発熱は体内のウイルスを除く働きであるとすれば、発熱は治療のプロセスと考えられ、軽々しく取り除くことは良くないとも言えます。
うつ病を例に挙げると、うつ病は人生の方向転換を促すプロセスという捉え方もあります。それまでは脳を酷使して生きてきた状況からの転換を促している、ということです。そう考えれば、うつ病が遷延化している場合、もしかしたら、人生の方向転換に取り組まないまま、症状だけを薬などでおさえにかかってしまっていることに起因するかもしれません。具体的に言えば、生活習慣(睡眠や食事など)がそのままである、仕事での働き方がそのままである、人生に対する価値観がそのままである、といったことです。
症状と自分の性格、資質との区別ができないということもよくあります。もっと言えば、「治る部分」と「治らない部分」とを勘違いしているようなケースです。多くは症状として治るにも関わらず、「これは自分の性格だからしようがない」として諦めてしまうようなケースです。これも機会を失い、もったいない結果となっていることがあります。
・未熟な自己治療としての症状、問題行動~他のリスクを軽減するために生じている場合
依存症などは顕著ですが、問題行動が自己愛の傷つきや居場所のなさを癒すために行われている解決行動である場合があります。そうしたケースでは、症状を取り除こうとすることがかえって、症状を強めてしまうことになります。
当事者の生育歴などを丁寧にヒアリングして、根本にある要因や、現在の人間関係の行き詰まりなどを解消する必要があります。
・変化への理解のズレ
変化があっても変化として認識できないために、かえって症状が強まる、ということがしばしばあります。たとえば、人間にとってストレスや不安といったものは生きている限り完全になくなることはありません。もし当事者が完全に不安がなくなることが変化だと設定していたとすると、変化があるにもかかわらず「変化がありません」と考えてしまい、そのことが不安を強める、ということがあります。慢性腰痛など心因性の身体症状も同様で、少しの痛みにもこだわるとかえって症状は強まることが知られています。
完璧主義な方、強迫傾向のある方や、発達障害傾向、相対的に知能指数の低いケースでこうしたことが見られるようです。
特にある種の発達障害では時間が連続しておらず全てが「今」としてとらえられるため、「今」がダメなら全てダメといった極端な考えになってしまうこともあります。
“変化”というものへの認識の偏りも問題になります。「変化とは、大きなもの。革新的なもの」という捉え方をしている場合も、かえって変化を妨げてしまいます。「変化とは怖いもの」ということも同様です。小さな変化でも変化としてとらえること、そうした積み重ねが本格的な変化を生んでいくことになります。
また、変化は変化した直後は顕著に感じますが、時間とともに薄れていく傾向があります。また、本質的な変化ほど、本来の自分に戻る、という形をとるために、自分にとっては自然でありわからないこともあります。こうしたことも理解がないと「変化がない」ととらえてしまうことがあります。
・家族や職場など環境からの影響
本人は変化への取り組みをしていて変化しているにもかかわらず、周囲がネガティブな言動を繰り返している場合。あるいは否定的な決めつけやレッテル、罪悪感を刷り込んでいるような場合。また、共依存傾向の関係者がいて、本人が世話をする対象でなければ困る、といった関係性である場合。子どものケースであれば、思春期に差し掛かり子離れしなければならないにもかかわらず関わりが続くような場合、変化が目に見えてこないことが生じます。
依存症などは「家族関係の病」とも呼ばれますが、そのほかの悩みでも家族や職場、友人関係が機能不全な場合に生じることがあります。機能不全とは例えば、過度な完璧主義、強迫的な傾向、本音を言えない、支配的な関係といったことです。人間は環境に強く影響を受ける存在です。少しずつ起こる変化に対しても「まだまだ全然よくなっていない」とフィードバックしていれば、本人も変化を感じることはできません。
とくに子どもの場合などに顕著ですが、機能不全家族に育つと自分がなくなる、自分が失われる、ということが生じます。勉強や仕事ができなくなったり、簡単な約束もまもれないというような状態になることもあります。醜形恐怖や不安障害、学校にいけなくなる、家庭内暴力と行ったことに発展する場合もあります。そんなときにお子さんをカウンセリングしてもほとんど改善が見られません。問題とされるお子さんの家族をカウンセリングすると問題が改善される、解決するということが珍しくありません。
・解決行動や“問題児”扱いが問題を長引かせている
上記と似ていますが、周囲(家族や職場など)が当人を「問題児」「病気」として扱っている場合にも問題が長引くことがあります。また、それらを「治そう」と解決しようとすること自体が「問題児」「病気」との暗示を裏付ける働きをして、問題を悪化させることがあります。依存症、パーソナリティ障害、ひきこもりや不登校などで顕著です。社会構成主義といいますが、精神障害は取り巻く環境で交わされる意識や言葉で作られる傾向があります。関係やコミュニケーション、解決行動の悪循環を取り除く必要があります。
・生活習慣の乱れ
睡眠、食事、運動、仕事など生活習慣を適切にすることはとても大切です。いくらカウンセリングを受けても、薬を飲んでいても、生活習慣が不適切なままでは良くなることは難しいでしょう。基本的には悩みを抱えるときとは生活習慣を見直す必要があります。うつ病などでは飲酒は避けなければなりません。特に、海外では、うつ病などは無理をしない範囲で外出、運動をしたほうがいいとされます。とくに極期を過ぎてもずっと家にいるような場合など、社会との隔絶そのものが復帰を難しくしかねませんので、適度に社会との接点を増やしていくようにしましょう。
・身体的な影響
甲状腺や副腎、腸、PMSといった身体的な要因も妨げとなることがあります。特に甲状腺などはたちまち重篤ではない不調として見逃されがちで、検査でも引っかからないこともあります。特に、お取り寄りなどの場合は痴呆や脳梗塞などが原因となっている場合もあります。
▶「境界例、難治性うつ病、人格障害などの意外な原因~甲状腺、副腎疲労など」
・医原病
医原病とは、医療行為が原因で症状が生じていたり、解決が長引いていることです。よく知られるのは、抗不安薬などの向精神薬を長期にわたり処方されていて薬の影響で症状が生じている場合があります。かつて批判されたようなやみくもな多量多剤処方は見直されていますが、当事者がしんどさを訴えるあまりやむなく薬が増えているということもあります。もし薬の影響で症状が出ている場合は、減薬、断薬によって症状はなくなります。
※もともと問題がある場合はそれ自体が解決するわけではありません。ただ、妨げとなっている要素が除かれることで本当の意味での解決に取り組むことができるようになります。減薬、断薬は必ず医師との相談、指示のもとに行うことが原則です。
→なかなか治らない(難治性、遷延性)長引く悩みの治し方については、下記をご覧ください。
※サイト内のコンテンツを転載などでご利用の際はお手数ですが出典元として当サイト名の記載、あるいはリンクをお願い致します。
(参考・出典)
「こころの科学 (2014年11月号) 178号 治療のゆきづまり」(日本評論社)
青木省三、村上伸治「大人の発達障害を診るということ」(医学書院)
神庭重信、黒木俊秀「現代うつ病の臨床」(創元社)
樋口 輝彦「難治性うつ病の臨床 -感情障害全般の治療から難治性への対処まで-(新精神科選書 3)」(診療新社)
野村 総一郎/編著「エビデンスに基づく難治性うつ病の治療」(新興医学出版社)
松下 正明/総編集「専門医のための精神科臨床リュミエール 15 難治性精神障害へのストラテジー」(中山書店)
など